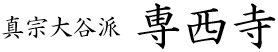専西寺沿革
当寺開山専西坊は源義家の末流で、俗名を源権之亟義持といい、宗祖親鸞聖人に深く帰依されていた篤信者であった。得度出家された後、専西坊という法号を賜り、承元元年(1207)、鎌倉雪の下に草庵を結び、一向山専西坊と号した。これが当寺の起りである。
その後、江戸時代に至り、時の住職釈正入法師は、徳川幕府のおひざもと江戸へ下り、俗名 青木勘次郎を開基に迎え、鎌倉雪の下より寺坊を本郷湯島三丁目に移し、改めて一向山専西寺と号した。時あたかも寛永三年(1627)であった。ここに宗祖親鸞聖人の教えに基づく報恩謝徳の念仏の声を江戸の街に響かせる道場が出現したのである。
当寺三世恵皆法師が住職であった天和二年(1682)、類焼の憂目に遭い、専西寺の所在地が新地、即ち新しく開けた住宅地に位置していたため、寺域を召し上げられ、寺号も取りつぶされるという法難に遭い、やむなく代々木の正春寺内へ移転。恵皆法師は、そのまま正春寺の住職として就任された。
その後、かつて当寺開山の釈正入法師の時代に、豊島郡駒込村の百姓内海左近圃角左衛門 より土地を求め、専西寺所有地として関係もあって、駒込の地に専西寺を再建することを条件に、正春寺の地位も南新法師に譲ることを寺社奉行に申し出た。しかし、「南新の住職は未だ若すぎる」との理由で却下され、仕方なく恵皆法師は、南新の後見人として正春寺に留まることとなった。
元禄五年(1692)、五代将軍徳川綱吉公の十三回忌法要が営まれた際、再び専西寺再興の件を申請したところ、「古跡」によりとの理由で許可され、喜び勇んで駒込の地に専西寺を再建した。
享保三年(1718)、再び類焼に遭い、翌年、現在の地に代替地を得て移転してきた。その後、第二次大戦の戦火によって堂宇すべてを焼失。鋭意、復興再建につとめ、昭和三十一年(1956)、鉄筋コンクリート造本堂を、昭和四十二年(1967)、木造の庫裡を完成、昭和六十三年(1988)、庫裡改築、 平成十八年(2006)、この度の本堂修復を終え現在に至っている。 (『本郷の寺院』より・一部加筆)
■ 沿革
■ 真宗大谷派とは
■ アクセス